

精神疾患の親と暮らす子ども・若者を支えるために、「家族支援とは何か」を多角的に問い直す全7講座。支援者・当事者・専門職の声に加え、スウェーデンの先駆的な実践事例からも学び、支援の再構築とつながりを育む学びの場です。
既存の支援の課題を多角的に検証し、新たなアプローチを模索します。
理論と実践、当事者の声を組み合わせた包括的な学習プログラム。
家族支援の本質を見つめ直し、真に必要な支援を考えます。
〜精神疾患の親と暮らす子ども・若者の実態と支援の全体像〜
13:00-14:50(90分講演+20分グループワーク)
東京都立大学教授
精神保健福祉士。博士(保健学)。東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻(精神保健学分野)博士課程修了。専門領域は、ソーシャルワーク技法,精神保健学、児童・思春期ケースワーク、家族支援など。主な著書は、『高齢者虐待防止のための家族支援』(共著、誠信書房)『高齢者虐待にどう向き合うか』(共著、瀬谷出版)『ソーシャルワーカーのジリツ』(共著、生活書院)『ソーシャルワーカーのミライ』(共著、生活書院)など。
〜支援の構造を問い直す〜
15:00-16:50(90分講演+20分グループワーク)
兵庫県立大学環境人間学部教授
専門は福祉社会学、社会福祉学。著書は『能力主義をケアでほぐす』(晶文社)『ケアしケアされ、生きていく』(ちくまプリマー新書)『「当たり前」をひっくり返す――バザーリア・ニィリエ・フレイレが奏でた「革命」』(現代書館)『家族は他人、じゃあどうする?――子育ては親の育ち直し』(現代書館)、共著に『「これくらいできないと困るのはきみだよ」?』(東洋館出版社)など。
〜精神疾患とともにある家庭へのトラウマインフォームドな関わり〜
9:00-10:50(90分講演+20分グループワーク)
兵庫県立尼崎総合医療センター小児科長、一般社団法人TICC代表理事
小児科医として、子ども虐待やその予防、トラウマを抱える子どもや家族への支援に長年従事。トラウマインフォームドケアの普及と実践を推進し、社会全体がトラウマに配慮した支援を行えるよう啓発活動や人材育成、地域実践事業を展開。虐待や犯罪などによる被害でトラウマを負った人々への支援、支援者の養成、調査・研究・広報・社会提言など、幅広い活動を行う。
〜精神疾患の親と暮らした子ども若者の声〜
11:00-12:50(90分講演+20分グループワーク)
当事者体験者
精神疾患の親を持つ家庭で育った子ども若者たちが、仮名で顔を出さずに語ります。一人一人が違う家庭環境で、それぞれの困難を抱えて生きてきました。親の病気への戸惑い、誰にも言えなかった孤独、成人しても続く葛藤。親への気持ちは日々変わります。「9月21日付の気持ち」として、その瞬間の揺れ動く思いを話していただきます。どんな支援が必要だったか、支援者の皆さんに届けたいことが聞ける場になればと思います。
〜精神疾患をもつ親子支援の法的視点から考える介入のあり方〜
10:00-11:50(90分講演+20分グループワーク)
弁護士、日本弁護士連合会子どもの権利委員会副委員長
名古屋大学大学院教育発達科学研究科教育科学専攻 修士(教育)。弁護士登録直後から、非行、虐待など子どもに関わる仕事を中心に従事。現職として、日本弁護士連合会子どもの権利委員会副委員長、名古屋市子どもの権利擁護委員など。大学の非常勤講師として「子どもの権利論」などを担当、子どもの権利に関する講演、自治体支援等も行う。共著に『子どもの権利ガイドブック(第3版)』(日本弁護士連合会子どもの権利委員会編著、明石書店)、『子どもコミッショナーはなぜ必要か』(日本弁護士連合会子どもの権利委員会編、明石書店)など。
〜精神科医の立場から見た家庭支援のリアル〜
9:00-10:50(90分講演+20分グループワーク)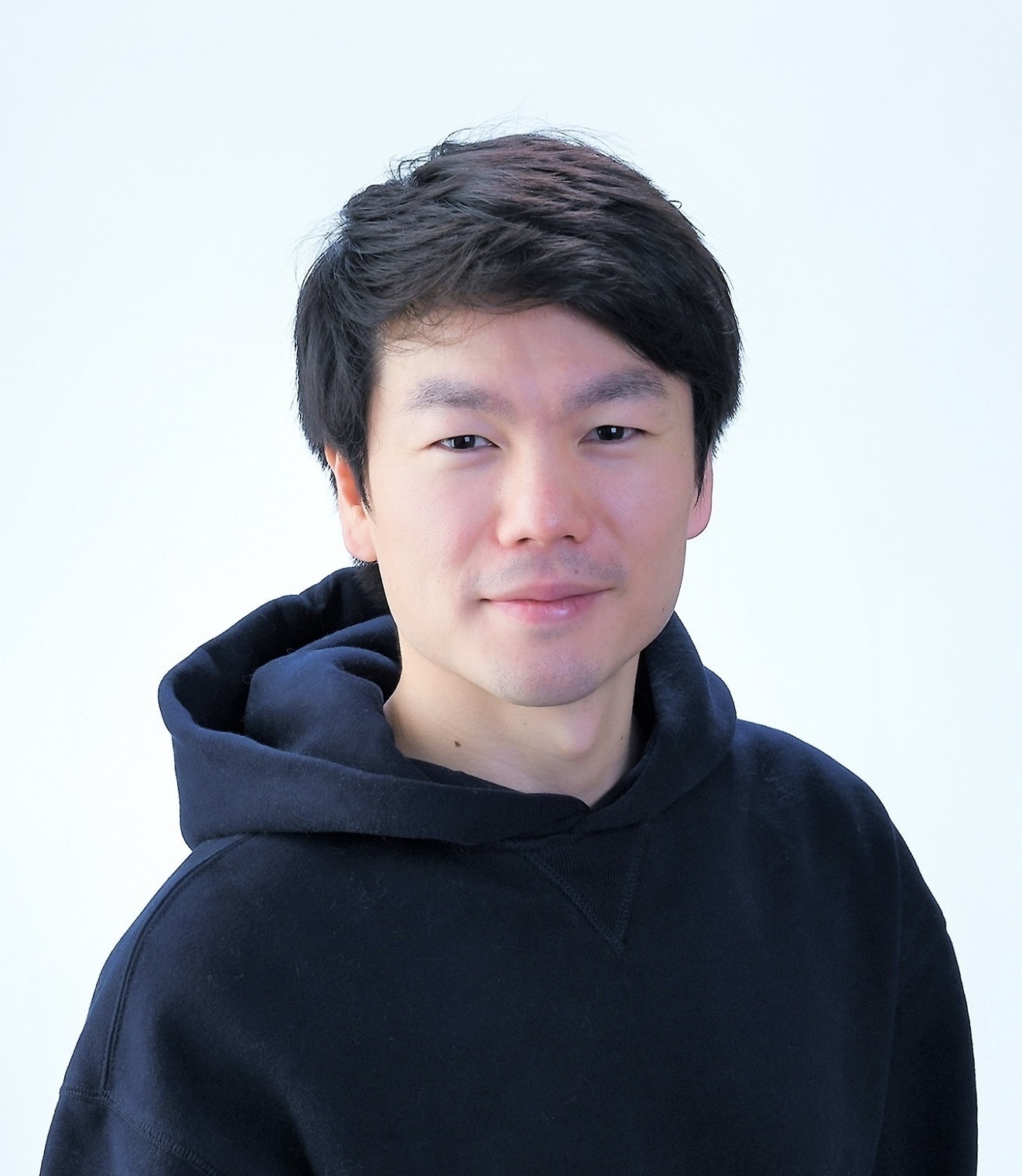
子どものこころ専門医、医学博士
山形大学医学部卒。慶應義塾大学大学院博士課程修了。児童・思春期に関連する国内外の研究に携わりながら臨床を行っている。幼少期を過ごした英国でのマイノリティとしての生活が原体験となり、子どもの居場所「はじまりの基地」を開設したり、知的/発達障害児・者サッカースクール「認定NPO トラッソス」チームドクターを務めるなど、子どもの主体性を引き出す団体の活動支援に力を入れている。著書に『10才からの気持ちのレッスン』(アルク)がある。
〜精神疾患のある親と暮らす子どもへの制度的アプローチ〜
17:00-18:50(90分講演+20分グループワーク)Maskrosbarn創設者/スウェーデン、関西大学社会学部教授

高校時代の2005年に友人と2人で活動を開始。現在は、困難な家庭環境にある子どもたちを支援する団体である、Maskrosbarnの事業開発責任者。当事者・経験者による団体というスタンスを保ちつつ、全国3ヶ所の拠点30人の有給フルタイム職員を有する規模に発展している。スウェーデン国内全ての子どものうち、約25%(50万人)が該当状態と推計されるとして、メディアやSNS等で積極的に発信・啓発を行っている。

関西大学社会学部教授。北ヨーロッパ学会理事、子どもアドボカシー学会学会誌編集委員など。専門は子ども家庭福祉、市民社会論で、主な研究フィールドはスウェーデン。子どもの権利をベースとして、子どもの声が届く社会の仕組みのあり方、親子を支える予防型支援のあり方を国際比較の観点から探求している。共著は、『新 世界の社会福祉 第3巻北欧』(旬報社)、『子どもアドボカシーQ&A : 30の問いからわかる実践ガイド』(明石書店)等。
ご質問やご相談がございましたら、下記フォームからお気軽にお問い合わせください。